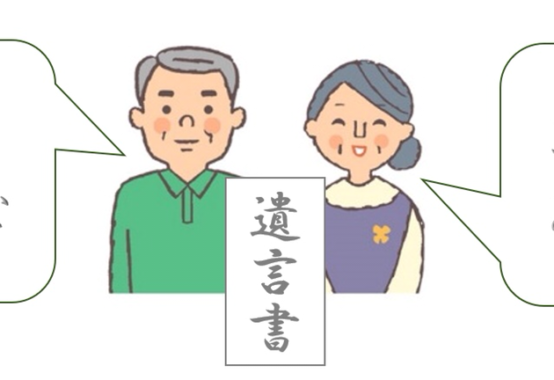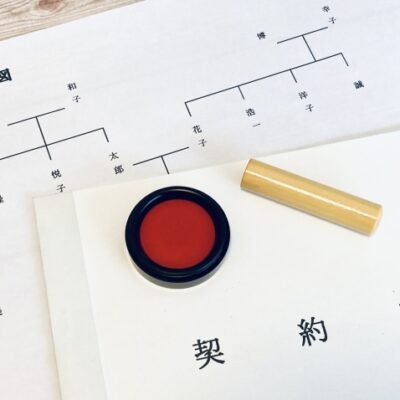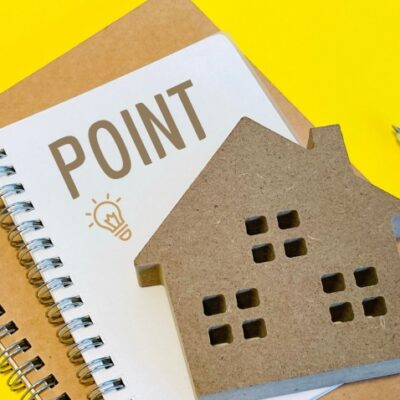【空き家予備軍と空き家対策】
全国的に空き家は増えてきており、空き家を相続する可能性は高まっています。
前回は、【相続で空き家にしないためにはどうすればよいか?】というテーマで解説しましたが、前回のコラムを読んでくださった読者の方からこんな質問が届きました。
Q「まだ空き家にはなっていませんが、将来的に実家が空き家になるかもしれないと思うと不安です。今から備えておきたいのですが、どのような対策があるでしょうか?」
このような空き家問題を未然に防ぐためには、まだ空き家になっていない
『予備軍』への対策が必要です。
そこで、今回は空き家予備軍について解説していきます。
<空き家予備軍とは?>
『空き家予備軍』とは、現在空き家ではないものの、近い将来空き家になる可能性が高い状態の住宅で、具体的には65歳以上の高齢者単身世帯が現在住む戸建住宅とマンションの持ち家を指します。
65歳以上の単身高齢者世帯は年々増加傾向にあり、2015年に約630万世帯、全体の約34%でしたが、国土交通省の調べによると2040年には約900万世帯で全体の約45%が単身高齢者世帯になる見込みです。
《国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(平成30年推計) 総務省「国勢調査」をもとに、国土交通省作成》
つまり近い将来、全世帯の半数近くが空き家予備軍になってしまうということです。
また、高齢化を背景に実際に空き家予備軍という言葉も各所で使われるようになってきています。
・大都市に空き家の「予備軍」が大量に潜んでいる。65歳以上の高齢者だけが住む戸建てとマンションの持ち家が東京、大阪、名古屋の三大都市圏に合計336万戸あり、同圏内の持ち家全体の2割強に達することがわかった。
(日本経済新聞 2018年6月22日)
・きたるべき大量相続時代に向けて、現時点で高齢者のみの世帯が住む住宅を「空き家予備軍」と捉え、空き家発生の予防に向けた取り組みも先送りしてはいけません。
(野澤千絵著 老いた家 衰えぬ街 住まいを終活する)
ここで空き家予備軍チェック!
みなさんも自分、親、親族の住む家が空き家予備軍に該当するかチェックしてみて下さい。
①子供達の住まいで同居する予定
②実家を離れ、子供達の住まいの近くに住む予定
③バリアフリ-マンション等へ住み替える予定
④高齢者施設等への入所を検討している
⑤現住まいが終の棲家だが、高齢夫婦のみの世帯
⑥高齢単身者で他に住み続ける親族等がいない
⑦高齢兄弟姉妹同居で他に住み続ける親族等がいない
⑧移住(Uターンを含め)を検討している
これらに該当する場合は空き家予備軍と言えるでしょう。
当てはまったという方も多いのではないでしょうか。
<なぜ空き家予備軍が増えているのか?>
- 高齢化
・高齢期に差し掛かった個人が長期入院や介護施設に入所するなど自宅へ戻ることが不確かになることで放置される
・団塊世代の高齢化に伴いその世代の相続で、空き家が急速に増加している
- 人口減少
・人口が減少することで住宅需要が下がり、多くの家屋が使用されずに残っている
- 家族形態の変化
・核家族化や単身世帯の増加により、実家を離れて暮らす人が増えている
- 相続
・国税庁によると、相続財産のうち約4割を土地と家屋が占めており、これが空き家の予備軍になる大きな要因となっている
・親世代の空き家を子供が引き継がない
-
金銭面
・売却、賃貸化が望ましいが、質や立地面で問題のある物件は市場性が乏しい
・売却、賃貸化できない場合、撤去されるべきだが、更地にすると固定資産税が上がるため、そのまま放置しておいた方がまだ有利
<いますぐできる空き家予備軍の対策とその手順>
世の中には空き家予備軍の問題で悩んでいる方々が大勢いらっしゃいます。
今回は、具体的な対策として売却と遺言書作成+死後委任事務契約の2つをご紹介します。
例1:Aさん(仮名)
「両親が高齢で、先日、父が体調を崩し、高齢者施設へ入所しました。
母は一人住まいが不安で、都内の私の家の近所のバリアフリーマンションへ転居を考えていますが、実家が空き家になってしまい管理等のことを考えると不安です…」
(解決策)
「売却して両親の老後資金に充当する」
1、信頼できる宅建業者の媒介(仲介) (一般の方などに売却)
2、リフォ-ム業者による買い取り (リノベ-ション商品として)
3、建売業者等による買い取り (新築建売物件用地として)
空き家問題は、空き家が「売れない」ことが問題の発端となります。
「売れない」理由は、空き家の価値が低いからにほかなりません。
・築年数が古い
・駅から遠い
・郊外
上記の3つは価値の低い空き家によくある条件ですが、この条件を「空き家予備軍」のうちに解消しておくというのも空き家問題に備える対策の1つです。
(解決までの流れ)
・所有者である父と相談者親族の意思確認
・所有者である父の認知能力・判断能力の確認
・現地調査(宅建業者などの専門家同行)
・物件調査(権利関係及び法令上の制限等)
・具体的解決策の提示(売却を提示)
・売却方法(業者による買取と媒介による売却)の説明
・売却手続のスケジュ-ル・段取り等の説明
・必要に応じて税理士による試算
(解決結果)
相談者様が「早期に解決してすっきりしたい」と1の業者による買取を希望され、お父様から相談者様へ売却に関し委任状を頂きAさんが手続きを進めて、
エリア内で建売をしている業者2社に買取価格査定を依頼し、金額も含めて好条件の業者と売買契約を締結し、無事売却出来て、ご両親の老後資金に当てることができました。長年お世話になった近隣の方々にも売却と引っ越しのご挨拶することができ、近隣トラブルを未然に防ぐこともできました。
例2:Bさん(仮名)
「夫に先立たれ、子供もいません。兄弟も皆他界し、いわゆるおひとりさまのため、私が亡くなったらおそらく空き家になってしまいます…。どうすればよいでしょうか?」
(解決策)
「遺言書作成+死後事務委任契約」
死後委任事務契約とは、生前に第三者(受任者)に、死亡後の事務を依頼する契約です。具体的には、依頼者が亡くなったあとの葬儀、お墓の管理、行政への届出、住居の明け渡し、親族など関係者への連絡、医療費や施設利用料の清算、ペットの世話、SNSアカウントの削除など多岐にわたり、希望に合わせて細かく決めることができます。
空き家の場合、死後委任事務契約を結ぶことで遺品整理や行政への届出などを依頼することができます。
ただし、死後委任事務契約では空き家の処分まではできませんので、遺言書を作成しておく必要があります。
1、現在の資産の確認と整理
2、遺言書の作成:公正証書遺言で遺言執行者を指定する
Bさんと相談のうえ、家は売却して、諸費用・租税公課を等を差し引き、手取り額をお世話になった親戚へ渡すという内容の遺言を作成しました。遺言執行者を指定しておけば、その方が相続の手続きをします、今回はBさんの親戚の方に内容をお伝えのうえ、遺言執行者になって頂きました。
3、死後事務委任契約の締結:このケースですと、家の売却は遺言書で対策できますが、死後の細々とした手続きまではカバーできませんので、死亡後の事務手続きや葬儀・納骨の手配などをご依頼頂きました。
(死後事務委任契約締結の流れについては※をご覧下さい)
4、墓じまい、永代供養
3についてもう少し詳しくご説明しますと、死後事務委任契約を締結する場合の大まかな流れは以下のとおりです
(解決までの流れ)
・本人の意向及び判断能力の確認
・財産等の調査把握・確認
・物件調査(権利関係及び法令上の制限)
・具体的解決策の提示(遺言書作成と事後委任事務契約の提示)
・公正証書遺言作成と死後事務委任契約のスケジュ-ル・段取り等の説明
・必要に応じて税理士による試算
(解決結果)
Bさんは公正証書遺言を作成して数年後にお亡くなりになり、死後事務委任契約に従って、まずは死後の事務や葬儀・納骨の手配をしました。
その後、Bさんの親戚が遺言執行者として相続手続きを進め、家の売却をサポート、無事に家は売却出来ましたので、家の相続登記を提携の司法書士に依頼しました。 そして、遺言書に従い、諸費用・租税公課を等を差し引き、残りは、受遺者の親戚へ渡りました。死後委任事務契約をしたことにより遺品整理等も業者にすぐに依頼でき、空き家の売却までスムーズに進行しました。
最後に、墓じまいをして、同じお寺の永代供養墓へ納骨しました。
※死後事務委任契約の流れ
【STEP1】依頼内容を決める
死後事務委任契約は、依頼者がどのようなことを代理人にやってほしいかを決めることからスタートします。どんな事項を依頼したいかは、ご自身が何を不安に思っているか悩んでいるかを書き出してみることからはじめてみるのをお勧めします。
【STEP2】代理人を決める
死後事務委任を依頼する代理人を決めます。弁護士、司法書士、行政書士などの専門家がおすすめですが、友人、親戚、社会福祉協議会なども候補になります。
【STEP3】契約書を作成する
死後事務委任契約の締結にあたっては、口頭などではなく、依頼者の生前の意思を明確化し残すためにも契約書といった書面を作成することが望ましいです。
【STEP4】公正証書化する
作成した書面は、公正証書化することが後日のトラブル防止の観点からも理想的です。公正証書とするにあたっては、公証人の手数料が別途かかります。必要な書類や詳細については弊社にお問い合わせください。
<もし空き家になってしまったら?>
いま空き家問題としてクローズアップされているのは、空き家として利用不可能ないわゆる「特定空き家」と言われているものです。
川の流れは待ってくれません。空き家問題は、早い段階での対策が重要です。空き家になる前(川上)の対策が、特定空き家(川下)を防ぐ鍵となります。
今すぐにできる空き家への対応3選!
-
空き家管理サービス:空き家の管理を代行するサービスです。空き家の所有者が定期的に管理できない場合に利用でき、清掃や点検、換気などの作業を行います。すぐに売却できない場合でも、このサービスを利用し空き家を健全な状態に保っておきましょう。
-
空き家バンク:空き家バンクとは、空き家の売却や賃貸を希望する所有者と、空き家を活用したい人を結びつける制度です。空き家の流通を促進することで地域の活性化や定住の促進を図ることを目的としています。空き家の状態や地域に関係なく物件を掲載することができます。
国土交通省 空き家・空き地バンク総合情報ページ
-
家いちば:買い手と売り手をつなげる不動産マッチングサービスです。家いちばのサイトを通じて売りたい人と買いたい人が直接やりとりでき、基本的に物件の内見や値段交渉等も当事者間でやるので、通常の不動産屋さんに依頼しても仲介手数料の高さ等から売れなかった物件が、売れたというケースも多数あります。筆者自身も家いちばを利用し、半年売れなかった物件が1か月で売却できた経験があります。
もし、空き家予備軍の問題でお悩みの方は、まずは上記のような方法を試してみるのもよいのではないでしょうか。
(まとめ)
今回は【空き家予備軍と空き家対策】について解説しました。
将来、空き家になることが懸念されている「空き家予備軍」は、年々増え続けています。
いざ、空き家になってからあわてることがないように、あらかじめ家族や親族で話し合っておくことが大切です。
(解決策が分からない方へ)
空き家や空き家予備軍の扱いについて、どのような選択肢がベストなのか、自身で判断するのが難しい場合は、一度、専門家である私たちに相談されることをおすすめします。私たちは空き家問題とは切っても切り離せない相続の専門家です。
さらに、空き家予備軍の売却に必要な不動産会社や不動産の名義を変えるのに必要な司法書士、税の試算に必要な税理士、葬儀や墓じまいに必要な葬儀社、遺品整理業者とも提携しておりますので、信頼して・頼れる専門家のネットワ-クを使い「ワンストップサービス」で解決策をご案内します。
空き家予備軍に該当し、空き家問題を未然に防ぎたい方は、まずはお問合せフォームから気軽にご相談ください。