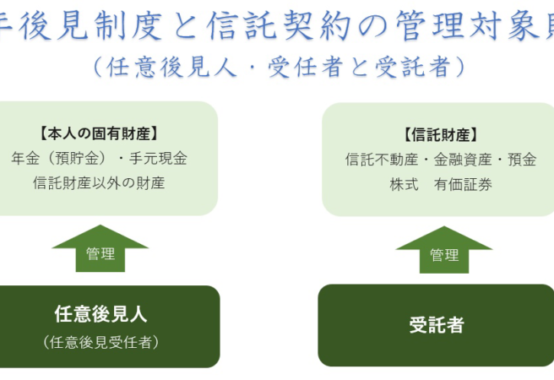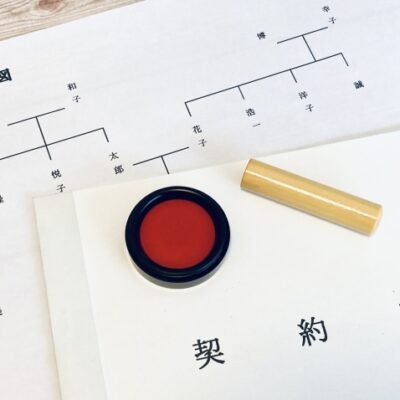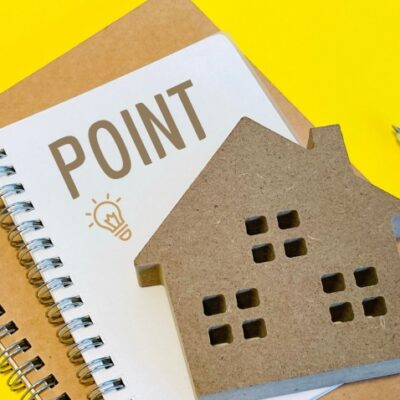【成年後見制度ってなに?】
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断が難しくなった人を、法律の面からサポートする仕組みです。たとえば、銀行での契約や施設の入居契約など、本人一人では不安なときに「後見人」が代わりに手続きをすることができます。
日本においては2000年に始まった制度で、
• ノーマライゼーション(誰もが共生できる社会)
• 自己決定権の尊重
• 身上保護の重視
といった基本理念を基に、家族や専門職が後見人となり、本人の暮らしを支えてきました。
制度は「後見(判断能力を欠く常況)」「保佐(判断能力が著しく不十分)」「補助(判断能力が単に不十分)」の三つに分かれ、本人の判断能力の程度に応じて法律行為を支援・代行する仕組みが整えられました。当初は高齢者だけでなく、障害のある人も対象とした「誰もが安心して暮らせる」制度として期待されました。
しかし、その成年後見制度が2026年に提出される見込みの民法改正案により見直されようとしています。
【どうして見直しが必要なの?】
課題の顕著化
成年後見制度は20年以上続いてきましたが、「使いにくい」という声が増えてきました。
• 一度始めると基本的に長期化する
原則として終了は「本人の死亡」か「能力回復による取消し」ですが、任意後見・補助・補佐については家庭裁判所に申立をすれば終了が可能です。もっとも手続きが煩雑なため、実際には本人が亡くなるまで続くケースが多く、「最後の手段」というイメージが強まっています。
• 後見人の権限が広すぎて本人の意思が置き去りになることがある
包括的な代理権が与えられるため、財産管理の合理性が優先され、本人の希望が十分に反映されないケースも指摘されています。
• 後見人を交代しづらい
現行法では「死亡」「辞任が裁判所に認められた場合」「不正や著しい不行跡」などに限られ、相性が合わないといった理由では認められにくい設計です。
• 利用するのに費用がかかる
成年後見制度を利用する場合、専門職(行政書士など)が関与すると一定の報酬が必要になります。
◦ 法定後見(後見・保佐・補助)の場合、家庭裁判所が本人の財産額や業務内容を考慮して報酬を定めます。一般的には月額で数万円〜程度となることが多いです。
◦ 任意後見の場合、報酬は本人と受任者の契約で自由に定められます。家庭裁判所は直接関与しませんが、任意後見監督人がついた場合、その監督人報酬については裁判所が決定します。
いずれの場合も、報酬は単なる「コスト」ではなく、専門職に依頼できる安心料といえますが、上記の様な理由から、制度の利用件数は高齢化の進展にもかかわらず伸び悩んでいます。最高裁の司法統計によると、2023年時点で新規申立件数は年間約3.5万件前後にとどまっており、潜在的な利用対象者数と比べると限定的です。
世界の潮流とその影響
障害のある人の自己決定権をより尊重すべきという国際的な潮流も背景にあります。2006年に採択された国連障害者権利条約は大きな転機となり、日本も2014年に批准しました。
従来の「代理意思決定」から、本人の意思に寄り添う「意思決定支援」への転換が国際的には主流となっており、日本でもより柔軟で本人本位の制度への改革が求められています。
【2026年からどう変わるの?】
現時点では検討段階ですが、法務省が2025年度内に要綱をまとめ、2026年通常国会に民法改正案が提出される予定です。成立すれば2026年以降に施行される見込みです。
• 「終わらない制度」から「終われる制度」へ
家庭裁判所が有効期間をあらかじめ設定でき、期間満了で終了する仕組みが検討されています。本人の能力回復や他の支援手段で代替できる場合も終了可能となる見込みです。
• 「包括代理」から「限定的支援型」へ
本人や家族のニーズに応じて、必要な支援だけを選んで依頼できる仕組みが検討されています。
• 後見人を変えやすくなる
「本人の利益のために特に必要がある場合」という柔軟な交代理由が新設され、相性や生活への適合性に応じた選び直しが可能になる見込みです。
• 報酬の透明化
業務内容に応じた報酬体系が明確化され、最高裁が全国的なデータを公表する方向で検討されています。
【改正スケジュールの見通し】
• パブリックコメント:2025年6月25日〜8月25日
• 2025年度内に要綱策定
• 2026年通常国会で民法改正案提出、成立後施行の見込み
【影響と準備アドバイス】
• 家族間で希望や将来設計を共有する
• 自身の意思(誰に・どのような支援を望むか)を文書で残す
• 制度に詳しい専門家(行政書士など)と関係を作っておく
【まとめ】
成年後見制度は2000年に始まって以来、20年以上にわたり多くの人を支えてきました。2026年の改正が実現すれば、制度は大きく生まれ変わる見込みです。
「守られる制度」から「自分らしく生きるために選べる制度」へ。
ご家族やご自身のこれからの安心のために、今のうちから準備を進めておくことをおすすめします。